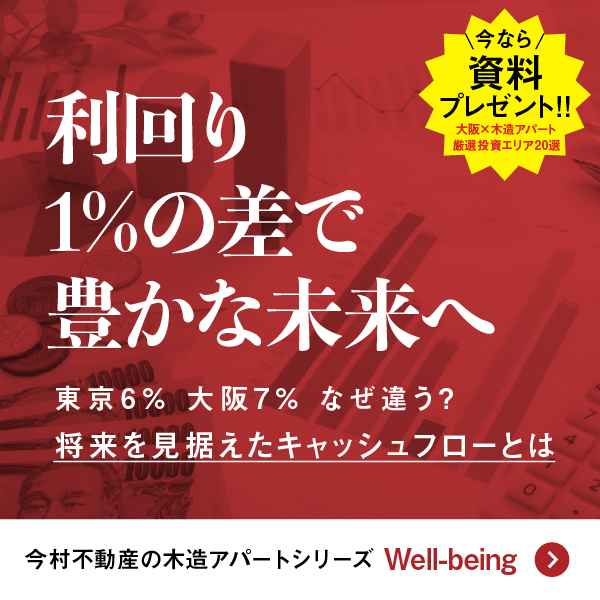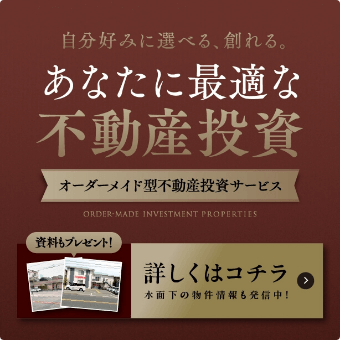不動産投資を始める、あるいはすでに実践している投資家の間で、近年ますます注目されているのが「損益通算」という制度です。不動産投資は収益が安定しやすい反面、ローン返済や修繕費、減価償却費などが発生するため、帳簿上は赤字になるケースも少なくありません。その赤字を他の所得と相殺することで、結果的に所得税や住民税の負担を軽減できるのが損益通算の大きなメリットです。
特に給与所得を得ているサラリーマンや、事業所得がある経営者にとって、損益通算は節税効果のインパクトが大きい手段となります。しかし2025年現在、税制改正や経費計上ルールの見直しも進んでおり、これまで当然とされていた節税手法が使えなくなるケースも出てきました。この記事では、不動産投資における損益通算の仕組みから節税効果、計算方法、最新の税制動向や注意点までを体系的に解説します。
目次
不動産投資における損益通算とは?

損益通算とは、異なる所得区分の黒字と赤字を合算し、課税所得を圧縮する仕組みのことを指します。日本の税制では所得が10種類に分類されていますが、そのうち「不動産所得」「事業所得」「譲渡所得」「山林所得」で発生した赤字は、給与所得や配当所得、雑所得などの黒字と通算できる仕組みになっています。
例えば、給与所得が500万円あり、不動産投資で100万円の赤字が出た場合、損益通算を行うと課税対象となる所得は400万円に圧縮されます。これによって所得税・住民税の負担が軽くなり、結果的に手取り収入が増えるという効果を得られるのです。
なぜ損益通算は節税に役立つのか

不動産投資は他の投資と比べても「必要経費」を計上できる範囲が広いという特徴があります。建物や設備の減価償却費、修繕費、保険料、管理委託費、さらには借入金利子など、経費計上できる項目は多岐にわたります。 特に減価償却費は現金支出を伴わないため、キャッシュフローには影響を与えない一方で、帳簿上は赤字を生み出す効果があります。つまり、手元資金は減らないのに税務上は赤字が発生し、それを損益通算することで税負担を直接軽減できるのです。所得税率の高い高所得層にとっては、この節税インパクトが非常に大きくなる点も見逃せません。
不動産投資における損益通算の計算方法

損益通算の計算はシンプルな流れで整理できます。まず本業の所得である給与や事業所得を計算し、次に不動産所得を算出します。不動産所得は家賃収入などの不動産収入から、減価償却費や修繕費、管理費などの必要経費を差し引いた金額です。そして最後に、これらを合算して課税所得を決定します。
具体例を見てみましょう。
ある投資家が年間で120万円の家賃収入を得ていたとします。一方で減価償却費や修繕積立金、管理費などの諸経費が合計で186万円かかった場合、不動産所得はマイナス64万円となります。この人の給与所得が500万円であれば、損益通算後の課税所得は436万円となり、その分だけ税金が軽減されることになるのです。
計上できる経費とできない経費
損益通算を活用する際には、どの支出が経費として認められるのかを正しく理解しておく必要があります。
経費として認められる代表的なものには、減価償却費、管理委託費、修繕費や修繕積立金、固定資産税や都市計画税、保険料、建物部分のローン利息、仲介手数料、広告宣伝費、水道光熱費、通信費、税理士報酬などがあります。
一方で、借入元本の返済や土地部分のローン利息(赤字の場合は対象外)、別荘やリゾート物件の損失、2023年以降に禁止された海外中古不動産の減価償却費、そしてスーツ代や罰金などの私的支出は経費として認められません。グレーゾーンの支出については、必ず税理士や専門家に相談するのが安心です。
2025年最新税制と注意点

2025年の税制改正では、不動産投資に関する損益通算のルールや経費計上に大きな影響が出ています。従来まで節税の柱とされてきた手法の中には制限が加わったものもあり、制度の最新動向を理解しておかないと、思わぬ税務リスクや損失につながる可能性があります。
まず、注目すべきは海外中古不動産の減価償却による損益通算の制限です。過去には、海外中古物件を購入し減価償却費を多く計上することで、損益通算を活用した節税が可能でした。しかし2023年以降、海外中古物件に関する減価償却費は原則として損益通算の対象外となり、2025年以降もこの制限が継続しています。これにより、海外物件を活用した「赤字で節税」という戦略は事実上使えなくなり、国内物件への投資や運用計画の見直しが必要です。
次に、土地取得に関わる借入金利子の損益通算制限にも注意が必要です。不動産投資で建物購入のためのローン利子は経費計上可能ですが、土地部分の借入金利子は赤字時に損益通算の対象外となりました。つまり、土地取得を目的とした借入を多くして赤字を作る戦略は、2025年現在では節税の対象にならないため、ローン構造の見直しが不可欠です。
さらに、税務当局は「意図的な赤字経営」への監視を強化しています。単純に税金を減らすためだけに赤字を作る行為は認められず、損益通算の適用にあたっては「事業性」や「継続的改善」が求められます。具体的には、収益を上げる努力や経費の適正化、建物の維持管理など、投資家としての行動が伴っているかどうかが判断基準です。節税目的のみで赤字を計上した場合、否認されるリスクがあります。
加えて、賃貸経営の規模や申告区分にも影響があります。青色申告特別控除(最大65万円)は、原則として「5棟または10室以上」の規模で事業的規模と認められる場合にのみ適用可能です。小規模な物件のみを所有している投資家は、損益通算や控除の恩恵が限定的になる点に留意が必要です。
最後に、2025年以降は経費計上の明確化も求められています。修繕費と資本的支出の区分、減価償却費の計上方法、ローン利息の対象範囲など、細かいルールが明文化され、税務署のチェックも厳格化しています。経費の取り扱いを誤ると、想定外の年度課税や追徴課税のリスクもあるため、税理士や不動産会社に確認しながら確定申告を行うことが不可欠です。
不動産投資における損益通算の落とし穴とリスク

損益通算は不動産投資における有効な節税策である一方で、活用を誤れば大きなリスクを抱える可能性があります。特に注意したいのは、キャッシュフローの悪化や長期的な赤字体質に陥ることです。帳簿上は減価償却費などによって赤字となり節税効果が得られていても、実際の現金収支が伴わなければ資金繰りは悪化していきます。長期にわたり赤字を続けると手元資金が枯渇し、物件の維持やローン返済に支障が生じる可能性があります。節税目的のみに偏った投資は、資産全体の健全性を損なう要因となるのです。
また、経費の計上についても誤解が生じやすい点です。不動産投資における必要経費の多くは損益通算の対象となりますが、土地取得費や土地部分のローン利子、別荘やリゾート物件の損失などは対象外とされています。こうした対象外の支出まで経費として計上してしまうと、税務署から否認を受け修正申告や追徴課税を課されるリスクが生じます。
過度なレバレッジも大きな落とし穴です。借入金を多用することで一時的に損益通算の効果が増しても、その裏側では返済負担や金利上昇リスクが大きく膨らみます。収益が安定しているうちは問題ありませんが、金利変動や空室リスクが重なれば、節税効果以上のキャッシュアウトが発生しかねません。特定の高利回り物件に偏った投資を行うことで分散効果を失い、資産全体の安定性が損なわれる点も無視できない問題です。
さらに、税制改正や税務調査のリスクも常に念頭に置く必要があります。不動産投資に関する税制は年々見直されており、過去には特定のスキームが規制されることもありました。節税効果だけを狙った赤字計上は調査対象になりやすく、不自然な経費処理があれば否認される可能性があります。税務署からの指摘を受けた場合、修正申告を余儀なくされるだけでなく、延滞税や加算税などの金銭的負担を強いられることもあります。
最後に、事業規模や申告手続きに関する要件を満たしていないこともリスクの一つです。青色申告の特別控除を最大限に活用するには「事業的規模」であることが条件とされ、原則として5棟または10室以上の賃貸経営が必要です。さらに、確定申告の際には帳簿や領収書、収支内訳書などを正確に整備しておく必要があります。こうした書類管理や事前の届出が不十分だと、本来受けられるはずの節税効果を失うだけでなく、最悪の場合は行政処分の対象となることすらあるのです。
このように、損益通算には確かに節税のメリットが存在しますが、同時に資金繰りの悪化、税務リスク、資産バランスの崩壊といった副作用が潜んでいます。必要に応じて税理士や専門家に相談し、長期的に安定した運用を意識することが、損益通算を安全に活用するための前提条件となります。
確定申告と実務の流れ

損益通算を適用するには、必ず確定申告が必要です。給与所得者であっても、不動産所得が発生した場合は年末調整だけでは完結しません。賃貸契約書、管理会社の収支報告書、固定資産税の通知書、ローンの残高証明書、修繕や保険の領収書などを揃え、「不動産所得の収支内訳書」とともに確定申告書Bに記入して申告します。
青色申告を選択すれば、事業的規模であれば最大65万円の特別控除が受けられ、赤字を最長3年間繰り越すことも可能です。規模が小さい場合には白色申告で対応可能ですが、節税メリットを考えると青色申告を検討する価値は大きいでしょう。
よくあるQ&A
Q1:損益通算で節税できる金額は?
→ 赤字分が課税所得から丸ごと控除されます。所得税・住民税率に応じて、最大で約45%分の節税効果があります。
Q2:不動産所得が20万円以下なら申告は不要?
→ 原則不要ですが、損益通算で節税効果を狙う場合は申告を推奨します。
Q3:毎年赤字になる物件の運用は安全?
→ 無理な赤字目的の投資はリスクが高く、資産価値やキャッシュフローを悪化させる可能性があります。経費の適正化と物件価値の見直しが重要です。
Q4:節税相談は誰に任せるべき?
→ 信頼できる税理士、不動産会社、資産運用コンサルなど、実務経験が豊富な専門家に相談することが安全です。
Q5:赤字が続く場合の繰越控除はどう使う?
→ 青色申告の場合、損失を翌年以降3年間繰越して黒字と相殺可能です。これにより、数年かけて節税効果を最大化できます。
損益通算は賢く活用し、健全な経営を
不動産投資における損益通算は、節税効果が非常に高い制度ですが、その活用には正しい理解と最新情報の把握が欠かせません。制度を誤って利用したり、無理に赤字を作り続けたりすれば、税務リスクや資金繰りの悪化を招く可能性があります。
重要なのは、損益通算を「目的」ではなく「手段」と位置付けることです。不動産投資の本質は、安定した資産形成と長期的な収益確保にあります。健全な賃貸経営を基盤としつつ、制度を正しく理解して損益通算を活用することで、節税と資産拡大の両立を実現できるでしょう。
私たち今村不動産では、中長期的に安定した利回りを実現し、投資家様の人生をより豊かで実りあるものにするWell-beingな不動産投資サービスをご提供しています。税務面についても専門家のサポートを受けることが可能です。もっと詳しく知りたい方は是非お気軽にお問い合わせください。
*今村不動産の新サービス「木造アパートシリーズWell-being」の詳細を見てみる