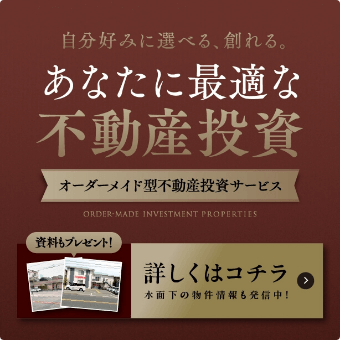アパート経営を行う上で、「減価償却」は極めて重要な概念です。この仕組みを正しく理解し、適切に活用することで、税負担を軽減しつつ、キャッシュフローを大きく改善できます。
本記事では、「減価償却とは何か?」から始まり、アパート経営における具体的な活用法・計算例・税務上の特例・確定申告のポイント、さらには経営戦略としての応用まで、丁寧に解説します。
目次
減価償却とは何か?基本の仕組みを理解しよう

減価償却とは、時間の経過や使用によって価値が減少していく資産の取得費用を、複数年にわたって少しずつ経費として計上する会計上の処理のことを指します。アパート経営においては、この減価償却の対象となるのは主に建物や附属設備、器具備品などです。
たとえば、アパート本体である建物や、給排水・電気設備といった附属設備、そしてエアコンや洗濯機などの高額な備品が該当します。ただし、土地は年月が経っても価値が減らないとされているため、減価償却の対象にはなりません。また、取得価格が10万円未満の消耗品類も原則として購入年度に全額を経費として計上することになります。
このように減価償却は、実際にお金が出ていかなくても帳簿上で経費を増やすことができるため、課税所得を抑えて節税することが可能になるのです。
なぜアパート経営において減価償却が重要なのか?

減価償却の最大のメリットは、毎年の課税所得を抑えられる「節税効果」です。減価償却費を毎年の経費として計上することで、課税対象となる所得が減少し、その結果、納める税金が少なくなります。
さらに重要なのが、キャッシュフローの改善につながる点です。減価償却費は実際の支出を伴わないため、帳簿上は経費が増えても現金は手元に残ります。これにより、税引後に残る現金が増え、資金繰りが安定するのです。
また、将来的な修繕費や設備更新費などの資金計画を立てる際にも、減価償却費の見込みを加味しておくことで、より現実的で無理のない経営プランを組み立てることができます。
減価償却費の計算方法|ステップと具体例

減価償却費の計算は、大きく分けて3つのステップで行います。
1.土地と建物の取得価額を分ける
アパートの購入費用には、建物だけでなく土地の代金も含まれています。しかし、前述のとおり土地は減価償却の対象ではないため、まずは建物と土地の価格を按分して、建物部分のみを算出する必要があります。この按分には、固定資産税評価証明書に記載された評価額の比率などが使われることが一般的です。
2.建物の構造ごとの耐用年数と償却率
建物の減価償却は「法定耐用年数」に基づいて行われます。耐用年数は構造によって異なり、それに応じた償却率を用いて計算します。以下に、主な構造ごとの耐用年数と償却率を示します。
建物構造ごとの法定耐用年数と償却率(定額法)
- RC造(鉄筋コンクリート造)
法定耐用年数:47年
償却率:0.022 - 重量鉄骨造
法定耐用年数:34年
償却率:0.030 - 木造
法定耐用年数:22年
償却率:0.046 - 軽量鉄骨造(鉄の厚みが3~4mm)
法定耐用年数:27年
償却率:0.037 - 軽量鉄骨造(鉄の厚みが3mm未満)
法定耐用年数:19年
償却率:0.053
3.実際の減価償却を計算する
たとえば、鉄筋コンクリート造(RC造)の新築アパートを2,000万円で取得したとします。土地部分を除いた全額が建物代と仮定すると、償却率0.022をかけることで、年間の減価償却費は44万円になります。
また、中古物件の場合は法定耐用年数をそのまま使うのではなく、「簡便法」によって耐用年数を再計算します。たとえば、築20年の木造アパートであれば、(22年-20年)+(20年×0.2)=6年が新たな耐用年数になります。この場合、償却率は約0.167となり、1,200万円の取得価額なら、年間約200万円の減価償却が可能になります。
確定申告での処理と税務特例

減価償却費は、確定申告の際に「青色申告決算書」に記載し、税務署に提出します。そのためには、対象となる資産について「固定資産台帳」を作成しておく必要があります。
この台帳には、資産の取得日や取得価額、種類、耐用年数、償却方法などを明記し、適切に管理することが求められます。
また、税制上の特例を利用することで、さらなる節税が可能です。たとえば、10万円以上20万円未満の資産は「一括償却資産」として3年で均等に償却することができます。さらに、30万円未満の資産であれば「少額減価償却資産の特例」により、その年に全額を経費として計上できる制度もあります(青色申告者のみ、年間300万円まで)。
減価償却を活用したアパート経営戦略

減価償却の仕組みを理解し、戦略的に活用することは、アパート経営における税負担の軽減とキャッシュフローの最適化において極めて重要です。とくに、建物と設備を分離して計上する処理や、中古物件における短期償却の活用、小額資産の即時償却などを組み合わせることで、減価償却費を最大化し、節税効果を高めることが可能となります。
まず注目すべきは、建物本体と設備を分けて資産計上する方法です。通常、建物の取得価額には設備部分も含まれていますが、これを電気設備、給排水設備、インターホン、エレベーターなどに分離し、それぞれの耐用年数に応じて減価償却を行うことで、初期数年間の償却費を大幅に増やすことができます。たとえば、RC造の新築アパートを1億円で取得し、そのうち2,000万円を設備として按分した場合、建物と設備を分けることで、初年度から3年間で年間約950万円の償却費を計上することも可能です。設備は耐用年数が短いため、建物よりも早く償却が進むという利点があり、これは節税とキャッシュフロー改善の両面で有効に機能します。
中古物件の特性を活用することも、大きな戦略の一つです。築年数が長く、すでに法定耐用年数を超えた設備については、残存価値を3年で償却できる特例が適用されます。たとえば、築15年を超える木造アパートの設備部分であれば、残りの価値を3年で均等償却できるため、短期間で減価償却費を最大化できます。木造の中古物件はそもそも法定耐用年数が短く(22年)、築古であるほど再計算された耐用年数が短縮され、結果として年間の償却費が大きくなるため、節税効果が顕著に現れます。
また、30万円未満の設備投資には「少額減価償却資産の特例」を活用することが可能です。この制度を用いれば、エアコンや防犯カメラ、宅配ボックスなどの比較的小型の設備について、取得した年度に全額を経費として計上できます。青色申告者であれば、年間300万円までこの特例を利用できるため、大規模修繕などのタイミングに合わせて集中投資することで、当該年度の課税所得を大きく圧縮できます。
設備投資を減価償却戦略の一環として行う際には、投資のタイミングと対象の選定も重要です。たとえば、看板(耐用年数3年)やインターホン(6年)など、短い耐用年数をもつ設備を優先的に導入すれば、より早期に償却効果を得ることができます。その際、工事明細書やメーカー見積書をもとに設備価格を合理的に算定し、建物価格との按分が客観的に説明できるようにしておくことが、税務調査対策としても有効です。一般的には、設備部分の価格は総工事費の10~30%程度と見積もられることが多く、過大評価にならないよう根拠を整備しておくことが求められます。
ただし、初年度から過度に減価償却費を集中させすぎると、償却が終了した数年後に税負担が一気に増加するリスクもあります。こうした初期偏重型の節税には、中長期的な修繕計画や設備更新スケジュールと連動させたバランスの取れた運用が必要です。また、設備投資とは別に、外壁補修や屋上防水などの支出については「修繕費」として全額をその年の経費に計上できるため、減価償却費との区分を明確にしておくことが経理上のポイントとなります。
このように、アパート経営における減価償却の戦略は、「建物と設備の分離計上」「中古物件の特例活用」「少額資産の即時償却」の三位一体で構成されます。とくに、築古物件において設備部分を3年間で償却する手法は即効性が高く、税務署に対しても十分な根拠資料を用意することで、制度を安心して活用できます。減価償却を経営戦略の中心に据えることで、安定したキャッシュフローと持続的な経営基盤を築くことが可能になります。
まとめ|減価償却を制する者がアパート経営を制す
減価償却は単なる会計処理ではなく、アパート経営を安定させるための強力な経営ツールです。正しく理解し、戦略的に活用することで、税金を最適化しながら、手元資金を厚くして経営の自由度を高めることができます。
今後アパート経営を始める、あるいはすでに物件を所有している方も、減価償却を含めたキャッシュフロー計画を立てることが、長期的な成功につながるでしょう。必要に応じて税理士など専門家の力も借りながら、自分に最適な償却プランを構築してください。
私たち今村不動産では、中長期的に安定した利回りを実現し、投資家様の人生をより豊かで実りあるものにするWell-beingな不動産投資サービスをご提供しています。アパート経営の減価償却や節税対策に関するご相談も専門家がプロの視点で的確なアドバイスをいたします。お気軽にお問い合わせください。
*今村不動産の新サービス「木造アパートシリーズWell-being」の詳細を見てみる