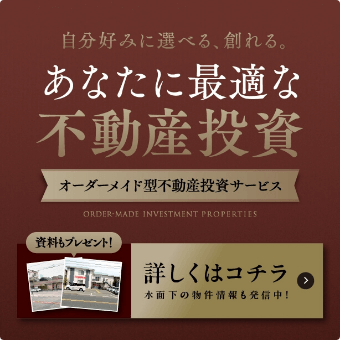アパートオーナーにとって関心の的である「サブリース2025年問題」。これは、2015年の相続税法改正をきっかけに増加したサブリース契約物件が、2025年に大幅な賃料見直しを迎えることで生じる経営リスクのことを指します。
この記事では、サブリース2025年問題の概要や背景、アパート経営者が取るべき対策などについて詳しく解説します。現在アパートオーナーをされている方はもちろん、これからアパート経営を始めたいと考えている方は、ぜひこの記事をお役立てください。
目次
サブリース2025年問題の背景と概要

サブリース2025年問題とは、2015年に急増したサブリース方式の賃貸物件が、2025年に大幅な賃料値下げに直面する可能性がある問題です。この問題は主に2つの要因から生じています。
相続税法改正とサブリースの急増
2016年1月1日に施行された相続税法改正により、相続税の基礎控除額が「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」から「3,000万円+600万円×法定相続人数」へと大幅に引き下げられました。例えば、相続人が一人の場合、控除額は6,000万円から3,600万円へと減少し、より多くの人が相続税の課税対象となりました。
この改正を受けて、相続税対策として不動産投資、特にサブリース方式のアパート経営が急増しました。不動産は現金や預金と比べて相続税評価額が低く設定されるため、相続税対策として効果的だからです。
サブリース契約の構造的問題
そもそも「サブリース」とは、物件オーナーがサブリース会社と賃貸借契約(マスターリース契約)を締結し、サブリース会社が入居者を募集して転貸する仕組みです。多くの契約では、オーナーに支払う家賃は満室時家賃の80~85%程度に設定されています。
しかし重要なのは、このマスターリース契約が借地借家法の適用を受けるという点です。借地借家法では賃借人(サブリース会社)の権利が強く保護されるため、サブリース会社からの家賃値下げ請求にオーナーが応じざるを得ない状況になりやすいのです。
なぜ「2025年」が問題なのか?

2025年が特に注目されている理由は2つあります。1つ目は、2015年に急増したサブリース物件が築10年を迎え、多くの物件で家賃見直しの時期となるからです。多くのサブリース契約では、最初の2年間は家賃が固定される条件で30年契約を結んでいますが、その後は市場状況に応じて見直しが可能となっています。
2つ目の理由は、2025年には団塊世代が全員75歳以上になり、人口動態の変化から賃貸需要の低下が予想されている点です。日本の人口に占める割合は約18%に達し、賃貸市場全体に影響を与える可能性があります。
サブリース契約の仕組みとリスク

サブリース契約は一見オーナーにとって安定した収入を約束するように見えますが、実際には様々なリスクを伴います。この仕組みを正確に理解することが、2025年問題への対策の第一歩となります。
サブリース契約の基本的な仕組み
サブリース契約では、物件オーナーとサブリース会社の間でマスターリース契約を締結し、サブリース会社が入居者と転貸借契約を結びます。オーナーにとっては、入居者募集や管理業務をすべてサブリース会社に任せられるという利点があります。
マスターリース契約は一般的に30年などの長期で結ばれ、オーナーへの支払い家賃(保証賃料)は満室時家賃の80~85%程度に設定されることが多いです。これにより、オーナーは空室リスクを軽減でき、安定した収入を期待できるという触れ込みで契約が進められます。
しかし、サブリース契約には重大なリスクが潜んでいます。それは、マスターリース契約が「借地借家法」の適用を受けるという点です。借地借家法では賃借人(この場合はサブリース会社)の権利が強く保護されます。つまり、サブリース会社から家賃値下げ請求がされた場合、オーナーはこれを拒絶したり契約解除したりすることが非常に困難なのです。
このような問題を受けて、近年ではいわゆる「サブリース新法」が設けられ、誇大広告や不当勧誘の禁止、重要事項説明の義務化などの対策がなされるようになりました。しかし、既存の契約については依然としてリスクが残っています。
経営計画への影響
多くのオーナーは、サブリース会社から提示された家賃収入を前提に住宅ローン返済計画を立てています。しかし、家賃が値下げされると、当初の返済計画が成り立たなくなるリスクがあります。特に、満室時家賃の80~85%という設定は、市場の変化や物件の経年劣化によって維持できなくなる可能性が高いのです。
2025年には、2015年に契約した多くのサブリース物件で家賃見直しが行われる可能性が高く、オーナーは想定外の収入減少に直面するかもしれません。これは単なる収益性の問題だけでなく、ローン返済が困難になるという深刻な事態を招く恐れもあります。
2025年に予想される具体的な影響

2025年にサブリース物件のオーナーがどのような影響を受けるのか、より具体的に見ていきましょう。これらの予測を理解することで、効果的な対策を講じることができます。
家賃値下げの規模と範囲
サブリース会社からオーナーへの大幅な家賃値下げ請求が行われることが予想されます。特に影響を受けるのは、2015年前後に相続税対策目的で建てられた物件です。これらの物件は、建設ラッシュにより供給過剰気味の地域も多く、競争激化によって今後、空室率が上昇する可能性が挙げられます。
立地による影響の差異
影響の大きさは立地によっても大きく異なります。都心部や交通の便が良い地域では、需要が比較的安定しているため、家賃下落の幅は限定的である可能性があります。一方、郊外や人口減少地域では、より大きな家賃下落に直面する可能性が高いです。
特に注意が必要なのは、高齢化率が高い地方都市です。団塊世代の全員が75歳以上となる2025年には、賃貸需要の年齢構成も変化し、従来のファミリー向け物件などでは空室率がさらに上昇する恐れがあります。
アパート経営のオーナーが取るべき対策と選択肢

2025年問題に直面するサブリース物件のオーナーには、いくつかの対策と選択肢があります。現状を正確に分析し、最適な戦略を選ぶことが重要です。
現状分析と早期対応
まず重要なのは、自身の物件の現状を正確に分析することです。具体的には以下の点を確認しましょう。
- 現在の契約内容(特に家賃見直し条項)
- 物件の市場価値と周辺の賃料相場
- ローン残高と返済計画
- 物件の修繕状況と今後必要となる修繕費用
早期に専門家(不動産コンサルタント、弁護士など)に相談し、個別の状況に応じた対策を検討することが重要です。
契約見直しの交渉ポイント
サブリース会社から値下げ請求があった場合の交渉ポイントとしては、以下が挙げられます。
- 市場相場データを独自に収集し、過度な値下げ要求には根拠を求める
- 物件の付加価値を高める改修提案と組み合わせた交渉
- 段階的な家賃引き下げの提案
- 契約期間短縮や解約条件の緩和などの代替条件
ただし、先に触れた「借地借家法」の適用によりオーナー側は交渉力が弱い立場にあることはきちんと認識したうえで、サブリース会社とのトラブルに発展しないよう、立ち振る舞いには十分気をつけましょう。
管理方式変更の検討
サブリース契約から一般的な管理委託契約への切り替えも選択肢の一つです。管理委託では家賃保証はなくなりますが、実際の入居状況に応じた収入が得られ、管理手数料も一般的にサブリースより低く設定されています。
ただし、この切り替えにはサブリース会社の同意が必要で、借地借家法の保護を受けるサブリース会社がこれを簡単に認めるとは限りません。交渉には専門家の助力が必要になることが多いでしょう。
物件売却という選択肢
場合によっては、物件の売却も検討すべき選択肢です。特に以下のケースでは売却を優先的に検討する価値があります。
- 大幅な家賃下落が予想され、ローン返済が困難になる場合
- 建物の老朽化が進み、大規模修繕が必要な時期に差し掛かっている場合
- より収益性の高い投資へ資金を移動させたい場合
売却すべきか否か、適切なタイミングなどに迷われた際は専門家に相談することをおすすめします。
ひとつひとつ、着実に。具体的なアクションプラン

これまでのことを踏まえ、サブリース2025年問題への対策としてアパートオーナーが取るべきアクションプランをまとめてみました。焦らずひとつひとつ着実に進めていきましょう。
短期的アクション(現在)
- 現在の契約内容を詳細に確認し、家賃見直し条項を把握する
- 物件の市場価値と周辺相場を調査する
- 財務状況の棚卸しを行い、キャッシュフロー分析を実施する
- 専門家(弁護士、不動産コンサルタント、税理士)への相談
- 複数のシナリオに基づく対応策の準備
中長期的な戦略(1~5年)
- 物件の差別化・付加価値向上のための改修計画
- サブリース契約から他の管理方式への移行検討
- ポートフォリオ全体の見直し(複数物件所有の場合)
- 売却も視野に入れた出口戦略の策定
- 市場動向を見据えた新たな投資戦略の検討
サブリース2025年問題を機に「より持続可能なアパート経営」に転換していこう
不動産市場は常に変化しています。今回のような法改正の動向など、最新情報は常に収集し、継続的に学習することが重要です。税制や法律の変化に応じて柔軟に軌道修正していくことも、不動産経営には欠かせません。
サブリース2025年問題も確かに大きなリスクですが、適切な準備と戦略があれば乗り越えられる課題です。この機会をアパート経営の見直しと改善のきっかけとして捉え、より持続可能で収益性の高い不動産経営を目指しましょう。
税制や法改正のキャッチアップなど自分ではなかなか手が回らない際は、提携している税理士など専門家のご紹介も可能ですのでお気軽にご相談ください。
また、私たち今村不動産では資産性の高い大阪の郊外エリアに着目した新しいアパート経営の形「木造アパートシリーズWell-being」を提供中です。安定した収益と将来的な資産価値の向上を目指しながら豊かなアパート経営をしていきたい方はぜひご活用ください。
*今村不動産の新サービス「木造アパートシリーズWell-being」の詳細を見てみる